体験者の戦後史という視点
「あんたたちは、沖縄戦の話しかわしらに聞かないんだね。わしらの戦争とは爆弾から逃げることだけだったんだね。戦後も苦しい思いをしてきたのに、それは聞こうとしない。なぜ、そのことは聞いてくれないんだ。」
ある体験者に聞き取り調査をした際に、ため息混じりで言われた証言だ。なぜ彼は、沖縄戦“時”だけでなく、沖縄戦“後”も聞き取りをしてほしいと訴えたのだろうか。体験者の戦後を見ていくことで、その意味を考えることができるだろう。そこで、本稿では「戦争被害受忍論」(以下、受忍論)という論理を引き合いにして、体験者の戦後がいかなるものであったのかという点について考えてみたい。
後半では、現在進行形の問題である辺野古新基地建設に遺骨の混じった土砂を使用するという問題について、受忍という視点から考えてみたい。この問題によって、どのような人々に受忍が強いられているのだろうか。そこを考えることで、私たちが考えなければいけない課題が見えてくるだろう。
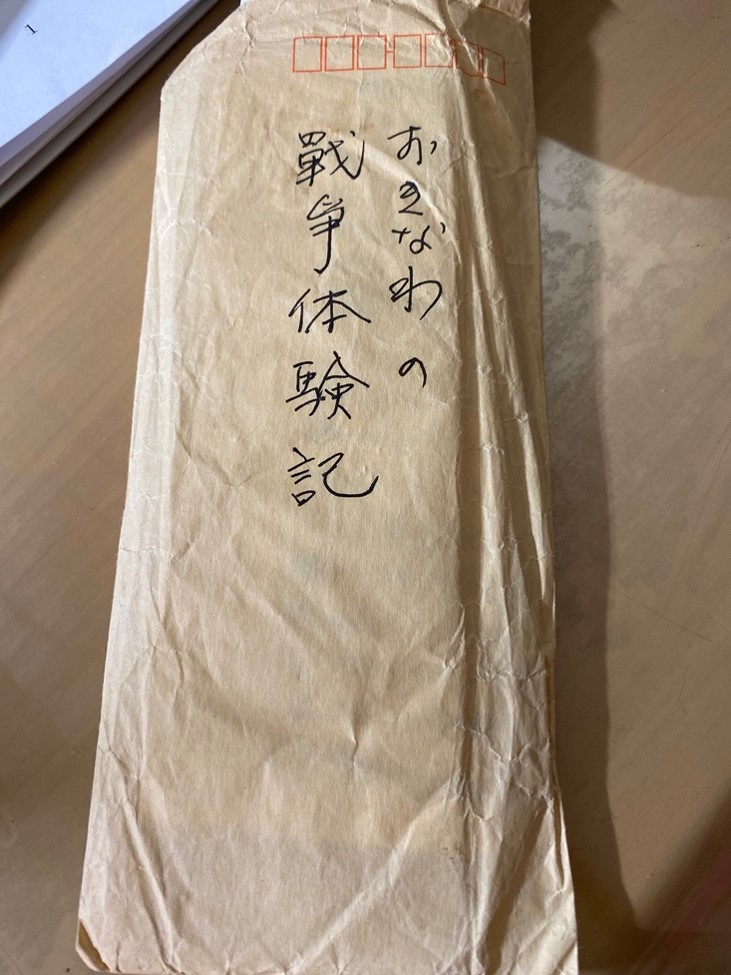
戦争被害は「等しく」受忍せよ、その言葉がもつ危険性とは何か
「戦争という国の存亡をかけた非常事態のもとでは、全ての国民は多かれ少なかれ、生命、身体、財産の被害を耐え忍ぶべく余儀なくされるが、それは国民が等しく受忍しなければならないやむを得ない犠牲であり、国家は被害を補償する法的義務を負わない。」
これが受忍論と呼ばれるロジックである。つまり、国家存立のためならば、国民の命を犠牲にしてもいいという価値規範が内在されている論理なのである。この論理の誕生は決して“戦前”ではなく、“戦後”生じた問題に対して受忍論を根拠に日本政府が「補償義務はない」とした点で注目に値する。
受忍論のリーディングケースとなったのは、1968年の「在外財産補償請求事件」である。1963年に第1審判決が下され、1965年に第2審判決が下されるが、受忍論が誕生したのは最高裁判決においてである。
1941年の開戦を受け、カナダに在住していた日本人の原告は、カナダにある所有財産を残したまま日本に引き揚げることとなった。敗戦後、1951年9月にサンフランシスコ講和条約の条約第14条a項(賠償・在外財産に関する規定)によって、現地の財産の処分権がカナダ政府に引き渡されたため、原告は財産の所有権を失うこととなった。
日本政府が引き起こした戦争によって、財産を失う事態が生じたのだから、それを補償するのは当然であるべきだと誰もが思うだろう。しかし、最高裁は、国の補償義務はないという「受忍論」を言い渡したのである。
受忍論は生命・身体の補償に対しても言い渡されている。例えば、沖縄戦の戦闘によって「集団自決」(強制集団死)で大怪我をした人、艦砲射撃によって怪我をしてしまった人、あるいは家族を亡くした人々など66人が、沖縄戦によって甚大な被害を戦後被ったとして国に対して補償を求め立ち上がったが、2018年の高裁判決で受忍論によって原告側の訴えを棄却し敗訴が確定した。
この事例は決して沖縄だけに限定されない。大阪大空襲の被害者においては高裁判決において、名古屋大空襲の被害者においては最高裁で受忍論を根拠に訴えを退けている。つまり、戦時中もっとも弱い立場に立たされ、国の戦争に巻き込まれていった民間人に対しての戦後補償はいまだ認められていないのだ。
受忍論では、国民が「等しく」受忍しなければいけないと謳っているが、そもそも戦争被害を「等しく」扱うことはできるのであろうか。艦砲によって手足を失った人々の苦しみ、沖縄戦で唯一自分だけが生き残った苦しみなど、一人ひとりに「戦争」によって生じた「被害」が存在する。そう考えれば、沖縄戦の被害を「等しく」同一視することはできないはずだ。