船漂着は信烈が17歳のころ。現場で見聞きした信烈は、その生き証人だったのだ。八重山史研究で知られる牧野清の『登野城村の歴史と民俗』には、その漂流記についての章があり、「マンデーラ人の若い娘たちは、毎日夕方は六―七百米も離れた中サクマ(大浜信烈翁宅)の井戸に、飲み水を汲みになど来たという」と記述されている。
卓爾と永珣が中心となった八重山郷土研究会には信烈も加わっており、マンデラ人漂流記もテーマとしていた(「八重山民報」1934年6月11日付)。
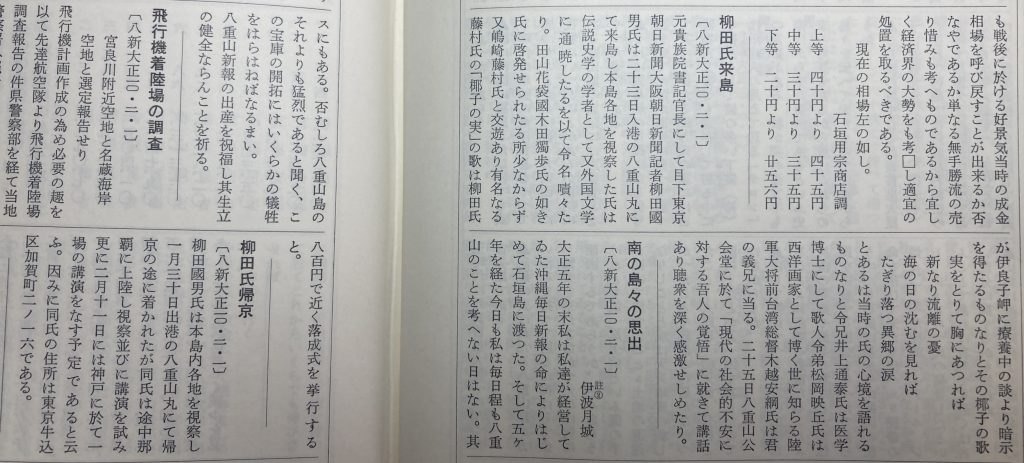
またハワイ大学教授デンゼル・カールが八重山調査した際、信烈から島の昔話、甘藷伝来、和蘭人と犬の話、漂流フィリピン人の話などを方言で聞き取りしている(「先嶋朝日新聞」39年8月6日付)。
これらを四つの資料を突き合せれば、「大濱君」は信泉だと判断できる。この時期、信泉も里帰りしている。弁護士試験にパスした信泉は、柳田が沖縄に向かった同じ12月に勤務先(三井物産)に辞表を出し、翌年4月に弁護士に転職するまでの4カ月近くは自由の身だった。この時期しか帰省の機会がなく、次はいつになるか分からないことを考えれば、故郷のお正月を楽しみたいし、数日の滞在だったとは考えにくい。信泉入港日は判然としないが、2月5日には信泉の歓迎会が母校で催されている(連載②の写真参照)。柳田の滞在(1月23日~30日)と重なっていたかは分からず、偶然同じタイミングだったかもしれない。ただ、おそらく顔を合わせていたと、筆者は推測する。
実は師範学校をラブレター事件で退学となった信泉が、東京の郁文館中学に編入した際、すでに島の後輩である宮良当壮が在学中で、二人は親しい仲だった。しかも柳田国男も郁文館中学卒業生であり、彼ら3人は同窓だったのだ。前述したように、言語学者の宮良に触発される形で柳田は南島に向かっており、宮良を通じてすでに接点があったかもしれない。東京から船で片道10日を要する時代。柳田は、師走に出発して年越しをはさんだ強行日程を組んでいるので、その数カ月前から現地関係者に訪問日や見聞きしたい事を伝え、手配もお願いしていただろう。むしろ柳田のほうが大浜帰省に合わせたかにも思える。古老の言葉や風俗を、日本の生活様式と比較したうえで日本語の学術語に翻訳するのに、大浜信泉ほどの適任者はいない。
たとえ大浜と柳田がすれ違いだったにせよ、島の語り部に耳を聳てて筆を走らせる柳田の眼前に、「大濱君」の姿が立ち現れていたことは確かだ。柳田は信泉の存在をしかと意識している。
それにしても、なんたる僥倖だろうか。八重山研究の父・喜舎場永珣から郷土の歴史を教わり、沖縄学の父・伊波普猷から学究への道を示されたのだ。近代日本を代表する知識人・柳田国男が故郷に足を運んで教えを乞い、その文化や芸能を称賛したことは大きな誇りになったに違いない。それゆえだろうか、大浜信泉は生涯、小島生まれであることや沖縄出身であることを卑下することがなく、日本人に対して劣等感を抱くような振る舞いを見せたことがない。同時代を生きた多くのウチナーンチュと比べて、それは信泉の極めて大きな特質だった。
(注1)NIE(Newspaper in Education=「エヌ・アイ・イー」)とは、学校などで新聞を教材として活用する活動のこと。日本新聞協会が中心となってNIE推進協議会を設立。同会協議会HPによると、「民主主義を支え、よりよい市民を作る」とされ、世界80か国以上で実施されている。1930年代にアメリカで始まったとされるので、八重山での取り組みは格段に早い。
(注2)喜舎場永珣は39年、町長から八重山神社建設に関する準備事務の嘱託を受けており、それには柳田が指摘した「八重山御嶽と日本古神社の類似性」が影響したのか興味深い。また国民精神文化研究所から八重山郡における郷土資料調査員としても嘱託を受け、開戦前年には大政翼賛会の八重山郡協力会議員に委嘱された。
永珣は昭和初期に新興宗教「生長の家」に帰依し、息子も入信させ親子で布教に努めた。超保守的・国家主義的だった「生長の家」の創始者・谷口雅春は敗戦後、GHQから公職追放を受けている。永珣は戦後も信徒の長老格として存在感を示し、八重山における「生長の家」発展の礎を築いた(「生長の家」八重山相愛会顧問の回想)。卓爾に仕えた測候所職員も信者幹部として名前を連ね、西表島測候所も活動拠点となった。永珣は、沖縄タイムス賞や柳田国男賞を受賞している。永珣の宗教観が、郷土研究や日琉同祖論とどう関連するのか。また戦時体制下で果たした役割をどう評価するかといった研究は乏しいように思える。