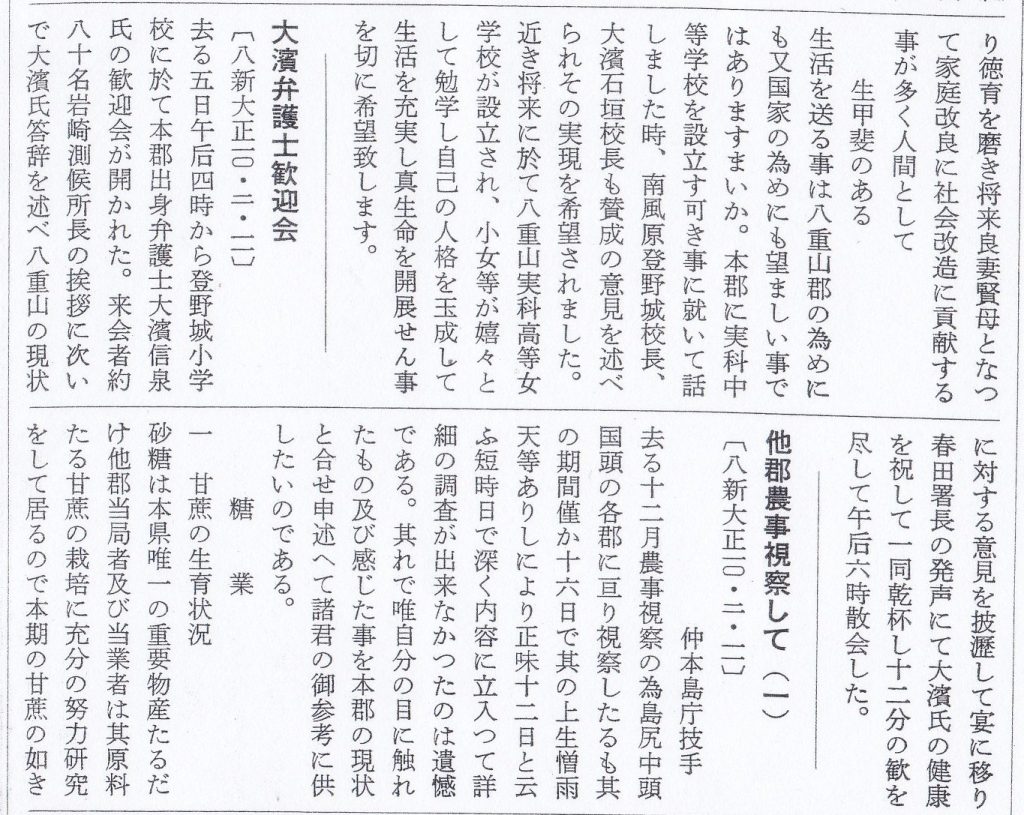今から130年余り前、石垣島に生まれた大浜信泉は周りの子どもたちと同じく、幼いころから山へ薪取りに行って家計を助け、肥料桶を担いで畑仕事を手伝った。小学校にあがる前に眼病を患ったため「ミーハギコーナー(目のはげた子)」いうあだ名がつき、当時十分な治療は受けられなかったものの、魚釣り、潮干狩り、バンシルー(グアバ)採りなど何をやっても一番上手だったという。日曜日には一日中、海で過ごしたが、ある日、遠い沖のリーフ(珊瑚礁)に金具を持って泳いで渡り、貝採りに夢中になったあまり、溺れ死にかけたこともあった。東京に出てからも「(エメラルドグリーンの石垣の海を)あの青さは世界に二つとないものだ。泳ぎなら誰にも負けない」と豪語した。身長165㌢、胸囲95㌢の堂々たる体躯で、70歳を過ぎても多忙な日程をこなしていくその「不死身」と称された身体は、故郷の大自然の中で鍛えられたものだ。
4歳の頃(1896年)、家の近くに、中央気象台(東京)直属の測候所が創設された。中国大陸沿い、太平洋と東シナ海に面する琉球諸島の測候所は、周辺の海路の安全を担う重要な役目を担っている。日本の気象観測の最前線として、南から北上してくる台風をいち早く察知しなければならず、暴風雨の強弱や進路予想を誤れば命にも関わる。気象科学に通じ、文明をまとった職員らが持ち込んだ日本本土の文物、新聞・雑誌は、地元職員をはじめとした地域の人々の眼にも触れ、ときには感性の鋭い学者や文化人を生むことがある(批評誌『N27 時の眼-沖縄』第7号に収録の仲村渠克「日本・沖縄を照らす「人工国家」 高良倉吉・仲里効・松島泰勝の「南大東島」」を参照)。
石垣島には、岩崎卓爾(宮城県出身)という稀有な日本人がいたことが、他の島々と比べて特別だった。この地で没するまでの40年近く、転勤を断ってこの島に暮らし、仕事の傍ら島の歴史・文化・民俗・自然の研究に勤しんだ。無類の子ども好きで、和洋を問わず読書家でもあった彼は地元民から愛されるようになり、「天文屋の御主前」(テンブンヤーのウシュマイ=測候所のおじいさん)と慕われ、「和製ガンジー」とも称された。巨大台風を観測中、強風に煽られた物が右眼に当たって失明、「片目の巌窟王」との異名も加わった。
戦後、芥川賞作家・大城立裕が小説に書き、それを基にしたNHK銀河テレビ小説「風の御主前」(山田太一脚本、1974年)が放送され、一躍世に知られるようになった。ルポルタージュや評伝が編まれ、中学校道徳教科書(学校図書)でも「郷土の伝統・文化の尊重、郷土を愛する心」をテーマに教材としている。齋木喜美子(関西学院大学教授)が一連の研究(『近代沖縄における児童文化・児童文学の研究』など)で、卓爾が全国的にも先駆的な児童文化活動に取り組んでいたことを確認。その裾野が広がる中で大浜信泉、喜舎場永珣(郷土史家)、宮良長包(音楽家)、宮良当壮(言語学者)、宮城文(社会活動家)、伊波南哲(作家)ら多彩な人材が互いに絡みあいながら活躍していったと指摘する。東京から一番遠い南の島で、なぜか大浜信泉の世代からは優れた人材―日本社会に適応したという意味で―が数多く出ており、彼らは日琉同祖論に寄り添い、また日本の海外進出に伴う映画史や植民地政策においても特筆すべき面があった。大浜信泉と卓爾が同じ島で暮らしたのは11年余り。信泉の人格形成期にあたるその11年は、新参者の卓爾が島に溶け込もうともがき苦しんでいた期間と重なる。大浜信泉のバックボーンを理解するためにも、当時の状況を詳細に紹介していく。