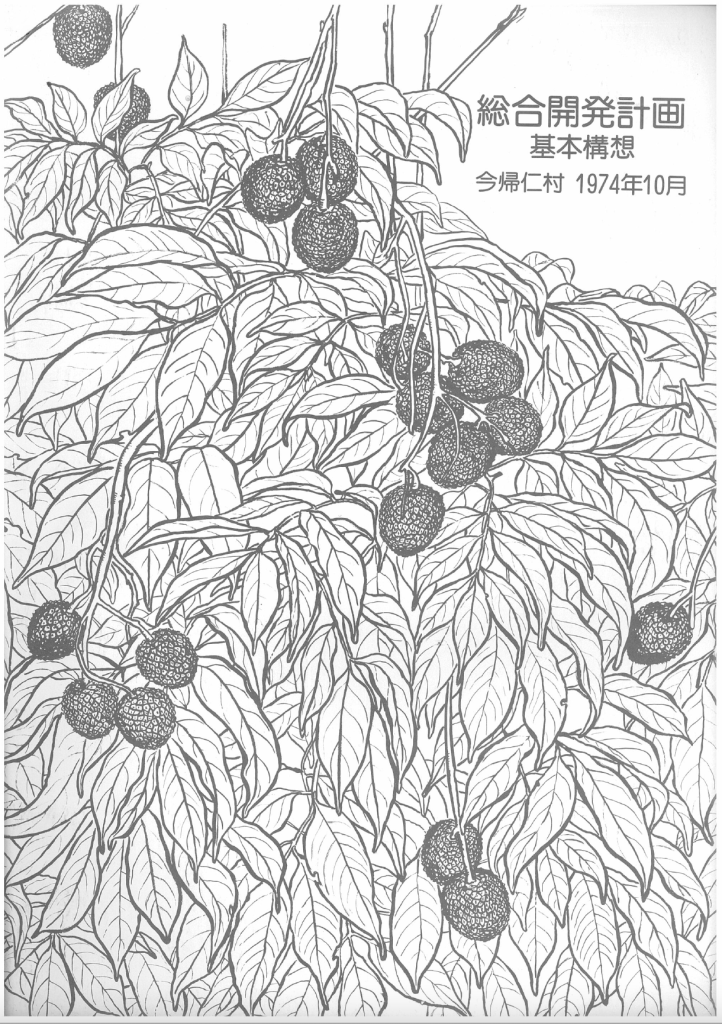竣工から43年目を迎える名護市庁舎。特異なデザインで際立つまちのランドマークをめぐって、地元・沖縄では保存か解体かの議論が静かに始まっている。当時、この建築の現場にかかわったのは、故岸本建男(元名護市長)をはじめとする名護市の若手職員と、本土の新進建築家グループ、象設計集団とその仲間たちだった。両者は、市庁舎建設に先立つ1970年代、「逆格差論」を掲げる『名護市総合開発・基本計画』の策定や、「21世紀の森公園」の整備にも深くかかわっている。本連載は、名護や今帰仁で起きた彼らの出会いと交流を、その場に立ち会った方々の証言から再構成し、「復帰」後の沖縄に垣間見えたもう一つの社会構想を紹介する。それは地域の自治と自立、消費経済に翻弄されない“貧しき豊かさ”への思想的試みであり、現在へ及ぶ日本社会の課題を浮き上がらせる視点でもある。
今帰仁村への旅
1970年夏、今帰仁城址を訪ねた中村誠司は、西日を浴びながら名護へ向かってゆっくり歩いていた。背中には大きなリュックサック。当時の流行り言葉でいう「カニ族」である。なぜ「カニ」かというと、駅の改札などで幅のある荷物をぶつけないよう横に歩く姿が似ていたからだ。
1台のクルマが停まった。彼の疲れ切ったようすを心配したのか、運転していた男がどこへ行くのかと尋ねてくれた。今帰仁の兼次[かねし]教会の牧師、村上仁賢だった。
広島大学地理学教室に在籍していた中村は農村調査を進めていた。国頭村奥間[くにがみそんおくま]に2週間ほど逗留して調査を行った後、今帰仁へ取って返すと村上を訪ねた。しばし世話になっているうちに、この土地が自分の人生に不可欠であることに気付く。中村と今帰仁の長いつきあいの始まりである。
中村は、地元広島の勉強会で広島工大の地井昭夫と知り合っていた。後に『名護市基本構想』に取り組んでいた地井に誘われて、「象」の面々と出会い、仕事を手伝うようになる。中村によれば、地理学の分析的な方法とプランニングの手法は真逆の関係にあるため、最初のうちはずいぶん苦労した、それでも地井に教わって要領をつかむと面白くなってきた。そんな折に今帰仁の計画策定の仕事が回ってきたのだという。長逗留ですっかり馴染んだ村をプランナーの眼で見つめ直していると、名護から送り込まれた平井秀一がやってきた。
名護の梁山泊にうんざりしていた平井は、リーダーの大竹から今帰仁へ行ってくれと言われ、放り出されたような気分になっていた。それでも昼間は中村と役場の田港朝茂と連れ立って村を歩き、人々の話を聞いて回った。村民が参加する「ムラづくり委員会」も立ち上げた。朝食も昼食も夕食も三人一緒。夕食の後は、宿所のすぐ裏に住んでいた中村と飲みながらあれこれを相談した。やがて不思議なことに苛立ちは治まり、村の生活や文化に対する関心が湧いてきた。後に平井は、今帰仁の方言地名をテーマに論文を書くことになる。
1974年から4年かけて、『総合開発計画・基本構想』(1974)、『土地利用基本計画』(1975)、『第一次産業振興計画』(1976)、『くらしの基本計画』(1977)という今帰仁村の4冊の計画書ができ上った。恩納村、名護市に続く計画書の中でもっとも緻密で充実したレポートである。それぞれの計画書の表紙に沖縄の見事な植物画を描いたのは、中村を路傍で拾ってくれた村上牧師である。
1975年には、象グループの記念碑的作品となる今帰仁村中央公民館が竣工した。コザのこどもの国に次ぐ建築作品は、村づくりの理念を形象化しただけでなく、「象」のその後の方向を示すものになった。