今年は沖縄の日本復帰から50年。この間、沖縄県政を担った歴代8人の知事の生い立ちから県政運営に至るまでを論じた野添文彬著『沖縄県知事 その人生と思想』(新潮選書)がこのほど発刊された。沖縄国際大学准教授の野添さんに著作に込めた思いを聞いた。
沖縄に生きた「生身」の人間のドラマチックな人生
――日本外交史や日米関係が専門の野添さんが「沖縄県知事」をテーマに選んだ理由は。
野添 これまで日米関係の観点から沖縄の米軍基地について研究してきましたが、沖縄を常に日米関係に翻弄される「受け身」の存在として描くことに違和感を覚えるようになったのが大きいです。逆に、沖縄側が主体としてどのように日本や日米関係、国際政治に影響を及ぼしたのか、沖縄からは日米関係や日本はどう見えるのか。そもそも「沖縄」とは何なのかについて、「保守」や「革新」といった括りを越えてそこに生きた「人」に焦点をあて、「沖縄基地問題」を考えたいと思ったからです。
――本書は沖縄県の歴代知事の人生を、ときには父親の代から掘り起こしています。
野添 沖縄で基地問題を研究し、ときに発信しながら、なかなか日本全国にこの問題が通じないというもどかしさがありました。そこで考えたのが、沖縄を「理解」するためには、何らかの「共感」が必要であり、これまでの「苦難」「差別」「怒り」といった(それはそれで事実なのですが)ものとは異なる「語り」(物語)が必要ではないかということでした。そこでは沖縄に生きた「生身」の人間のドラマチックな人生を通して、沖縄の激動の歴史や現状に関心を持ってもらえないかと考えました。そして、沖縄を象徴する人物であり、基地問題などの課題の矢面に立ってきた知事の人生に注目しました。
執筆して考えたことは、どの知事の人生もまさに沖縄の激動の戦後史を象徴するもので、同時にそのような激動の歴史を生きてきたことがそれぞれの知事の強い個性を形成し、それが沖縄政治をダイナミックにしてきたのではないかということです。同時に、「保守」であれ「革新」であれ、どの知事も米軍基地が沖縄に集中するという構造的問題に苦悩・苦闘し、ときに日本政府に対決し、また「苦渋の決断」といわれるような妥協的対応をせざるを得なかったということです。こうした歴代知事の葛藤は、基地集中という日本の安全保障政策や日米安保の歪みを示しています。
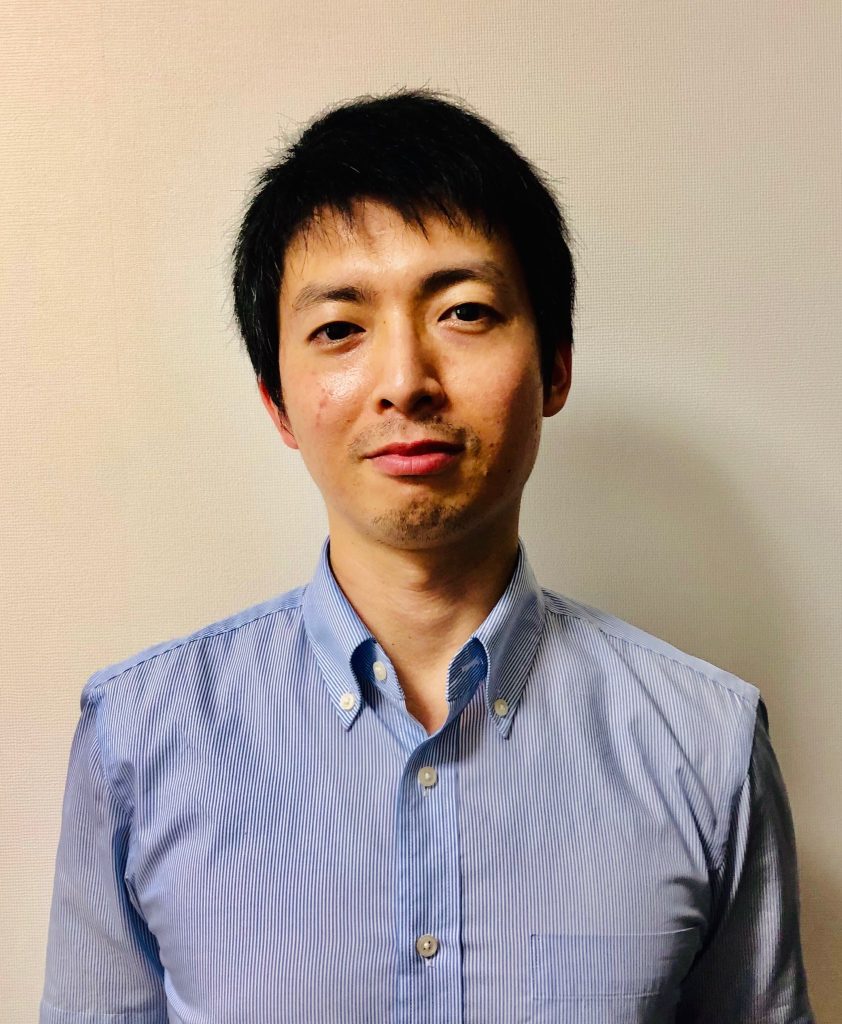
【著者プロフィール】
沖縄国際大学法学部准教授・野添文彬さん/(のぞえ・ふみあき)1984年、滋賀県生まれ。一橋大学経済学部卒業後、同大学大学院法学研究科博士課程修了。博士(法学)。専門は国際政治学、日本外交史・日米安保・沖縄米軍基地問題。主な著書に『沖縄返還後の日米安保 米軍基地をめぐる相克』(吉川弘文館、2016年)、『沖縄米軍基地全史』(同、2020年)など。