1面トップ連発の地元紙
では、沖縄の県紙、沖縄タイムスと琉球新報はどうか。
8月13日付夕刊で先行した沖縄タイムスは、同日中に号外を発行。翌朝刊1面はアテネ五輪が小さく入ったのみで、2、3面まで9割方が関連記事で埋め尽くされた。さらに見開きのグラビアに見開き特集、社会面もほとんど事故の記事で、四コマ漫画さえ定位置の第1社会面左上から下部におろし、めったに動かすことのない最終頁の番組欄まで内側の面に移動して関連記事で埋め尽くしている。

琉球新報もその日号外を発行。翌14日付朝刊の1面、総合面、社会面は事故の記事でほぼ埋め尽くされ、1面のアテネ五輪はわずか23行。やはりグラビアのページを組み、さらに社会面の四コマ漫画をこの日ははずすという異例の決定をしている。

タイムスは14日付から、新報は15日付から総合面で、事故の検証と県内外の政治的な動きを探る連載を始める。続報も連日1面に掲載され、8月中の両紙で、事故関連記事が1面トップでなかったのは、朝夕刊合わせて、タイムスが3回、新報が6回。社説で取り上げた回数はタイムス9回、新報8回。朝日、毎日、産経が14日付の1面トップに据えた「巨人オーナー辞任」は、いずれも関連記事を含めてその日のスポーツ面に入っていた。
地元の大事故なのだから当然と言えば当然かも知れないが、新聞における沖縄と「本土」のこれほどの隔たりは何なのだろうか。
ナベツネ氏は巨人のオーナーを辞任しても「球界のドン」であり続けたわけで、その後のプロ野球界がどの程度変わったのかはともかく、沖国大での米軍ヘリ墜落が日本の外交・防衛政策にもたらした影響は、さまざまな意味で甚大だった。
事故の翌日、沖縄県警は現場検証を申し入れたが、アメリカ海兵隊は拒否。これにより日米地位協定の不平等な規定が大きな問題となり、外交問題に発展していく。今日まで抜本的改定の道筋はまったく見えない。地元では、普天間の危険性に対する危機意識はさらに高まり、早急に閉鎖、返還を求める声が広がりを見せる。一方、政府も危機感を持ち、一進一退が続いていた名護市辺野古での代替基地建設計画を強硬路線へと次第にギアチェンジ。その姿勢は現政権にも受け継がれている。沖縄という一地方の事故にとどまらず、日本の政治を大きく揺さぶる大事件だったのは明らかだ。
現場を抱える地元の報道と他地域のそれに、量的な差が出るのはある程度は致し方ない。しかし、沖縄県紙と「本土」を拠点とする全国紙の報道の量的な隔たりは、明らかに異質だ。
そのことを考えるために、さらに古い新聞を引っ張り出して読み直してみたい。沖国大事故から27年前、今から43年前の報道である。
ファントム墜落
1977年9月27日。振り返れば、この日は敗戦後日本の分岐点のひとつにもなり得たと思う。
当時の新聞記事から要約する。午後1時20分ごろ、横浜市緑区(現・青葉区)の住宅地に、アメリカ海兵隊のRF4Bファントム偵察機が墜落した。機体は爆発して飛び散り、住宅2棟が全焼。主婦、子どもら5人が大やけどを負って搬送され、3歳と1歳の兄弟が未明に死亡した。2人の兄弟の母親(当時20代)も全身に大やけどを負い、4年にわたる治療の末に亡くなる。一方、同機の乗員2名は墜落前に脱出して無事だった。
以下は事故の一報を載せた各紙である。朝日は翌28日朝刊1面の3番手。毎日は27日付夕刊1面中央の記事で速報したものの、翌朝刊の1面にはなく、第1社会面のマンガ下。読売は27日夕刊1面に速報、翌朝刊1面は3番手左下、および第1社会面左カタ。日経は、28日付朝刊1面にはなく、社会面の中央。サンケイは28日付朝刊1面に写真記事、および第1社会面左カタ。東京は、27日付夕刊1面に速報、翌朝刊は1面にはなく、第1社会面左カタ――。





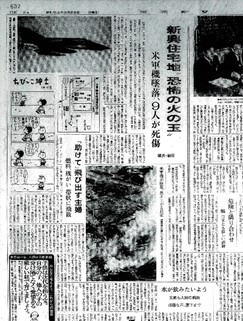
直後の報道で比較的手厚いのは読売だ。夕刊に速報を突っ込み、朝刊も1面に本記を入れ、社会面の受け記事にも紙幅を割いている。今どきの感覚からいえば、やや意外な印象さえあるが、この時代は、「右、左」「政権寄り、反政権側」のような新聞に対する世評の差は今ほどにはなかった。
しかし、その読売もトップにはしてない。この日はほかにも大きなニュースがあった。見ての通り、同じ日の夜、マレーシア・クアラルンプールで、乗客乗員79人が乗った日本航空のDC8旅客機が墜落した。これほどの大事故がトップ級であるのは間違いない。朝日と東京新聞は日航機が1面トップに置いている。
毎日、読売、日経、サンケイの4紙は、社会党(現・社民党)の新委員長の就任問題だった。この時、野党第一党だった社会党では、参院選敗北の責任をとって委員長が辞任。後任に飛鳥田一雄氏の就任が決まりかかっていたが、党内抗争のため同日の党大会で白紙になる。最終的には飛鳥田氏は委員長に就任するのだが、この時点での肩書は横浜市長。市民が犠牲になった事故の発生で、抗議声明を発したことが小さな記事になっている。
安保条約によって日本に飛来したアメリカ軍機の墜落により、日本人の幼子が亡くなるという悲劇的な惨事の「ニュース価値」は、海外での日航機墜落はもとより、社会党委員長の去就よりもさらに重要度が低い、というのがこの日の新聞各紙の判断だった。
地元紙の社説
ファントム墜落の報道という観点から考えると、不運が重なる。事故の翌日、インド・ムンバイ空港を離陸した日航機を、新左翼系組織「日本赤軍」の武装グループがハイジャック。バングラデシュ・ダッカの空港に強行着陸し、乗客・乗員を人質に日本で拘束されている過激派の釈放を要求する。「ダッカ事件」である。超弩級の国際事件の発生により、これ以後、全国紙各紙でのファントム墜落報道は、神奈川県内向けの地域面が中心になっていく。兄弟の母親の死や負傷した被害者の提訴、判決など以外は全国ニュースの扱いではなくなってしまう。
私は当時、高校生だった。ほかのニュースよりもファントム墜落の惨事に強い衝撃を受けたことを記憶しているが、最近はそれなりの年齢で米軍基地問題に関心を持つ人でさえも、この事故を知らない人がいて驚かされることがある。報道のあり様も影響していると考えられる。
事故現場の地元の神奈川新聞もその点は大差なかった。発生翌日朝刊の1面は、社会党委員長、日航機墜落の下の3番手。社会面は見開きではあるもの、その後は地域面が中心になってしまう。記事の量だけを見ると、沖国大事故のときの沖縄の2紙とは、申し訳ないが雲泥の差と言わざるを得ない。
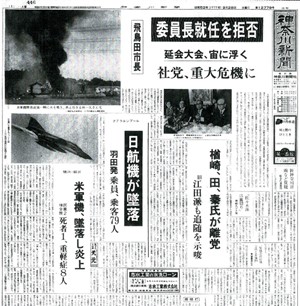
しかしながら、同紙には決して見過ごしてはならない記事があった。事故の8日後、10月5日付の社説である。「米軍機事故と地位協定」と題し、こう記している。
「日米地位協定が、いかに自主性のない対米従属的なものであるかは、いままでに多くの学者や法律家らによって指摘されているところである。そのことはまた、基本となる日米安保条約そのものを、米国と軍事条約を結んでいる諸外国の例と比べても明らかである」
横浜でも沖国大とまったく同じことが起きていた。現場検証は日米合同となったものの、主導権を握ったのは米軍で、「県警はそれを見守るばかりであったといわれている」。この後、米軍が、事故機のエンジンを日本側の承諾なく本国に持ち帰ったことが大きな問題になる。
社説はこう続く。
「わが国では安保条約、それに基づく地位協定、特別法など、憲法に基づかない法体系によって、われわれの生活が規律されている面がある。つまり、法規範的には、憲法体系は安保法体系に優先しているにもかかわらず、その政治への実現過程では、後者が前者を抑え込み、切り崩す形で二つの法体系が併存・対立し続けているといえよう」
今日までに日本社会が何度も直面し、全国知事会が見直しを提言するなど、ようやくその改善に声が上がり始めた日米地位協定の不平等規定。43年前、実際に起きた事故から地方紙がその事実をすくい上げ、指摘していた。しかも不平等の背後では「安保法体系」が「憲法体系」を凌駕し、国民生活を脅かしていることまでも明確に突き付けている。全国紙こそがその問題に注目し、全国ニュースとしてたゆまず国民に問いかけ続けるべきことだった。こうして見ると、単純な記事の大きさとは違う、また別の問題が見えてくる。