―日米修好通商条約は教科書で習いますが、琉米修好条約があることを知らない日本人は多いと思います。
前田 当時、米国が最短コースで中国へ向かうには、汽船の燃料になる石炭を保管しておく寄港地が必要でした。鎖国中だった日本以外で寄港地を確保する必要に迫られた米国に目をつけられたのが、琉球と小笠原でした。ペリーは1854年、琉球を独立国家とみなし、琉米修好条約を結びました。同時期に琉球はオランダ、フランスとも条約を結んでいますが、批准に至ったのは米国のみです。フランスは琉球を独立した国家としては見づらいと判断したわけです。
琉球国にとって米国が重要になってくるのは琉球処分の時期です。琉球側は「条約締結国が併合されようとしているのだから助ける義理があるでしょう」と米国に働きかけました。米国は「琉球の主張は正しい」と認識しながらも、日本と琉球を天秤にかけたとき米国は琉球を助ける利益がない、日本と良い関係を構築したほうが米国の利益になるという論理で黙殺します。
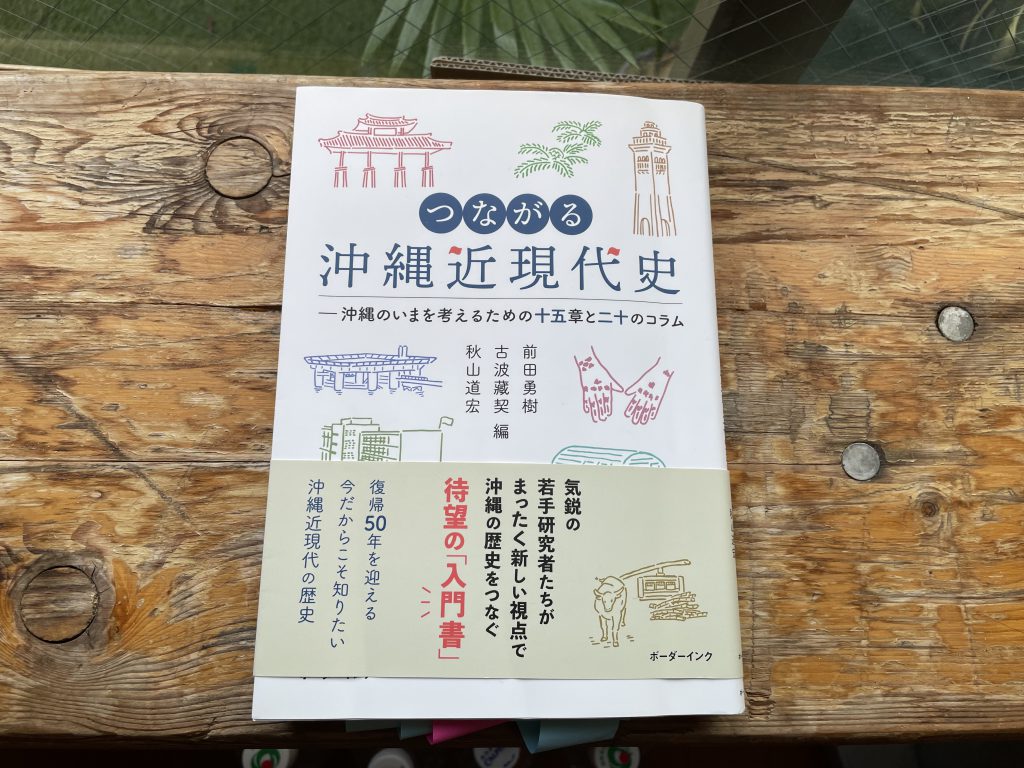
―中国(清)は琉球処分に反発しましたね。当時の日本が琉球をどう見ていたのかを推し量る上で、「改約・分島」交渉が参考になります。
前田 中国との関係の中で、今の沖縄県の形が維持されなかった可能性があったということですね。日本と清の改約・分島交渉は、日本が清国内の通商権を得る見返りに、宮古・八重山を清に割譲する内容でした。明治政府が琉球の分割統治を外交カードとして切っていたのは確かです。ただ、私が注目しているのは当時の沖縄社会でも、日本と清の間で戦争になるかもしれない、という緊張感が日清戦争(1894~95年)まで続いていた事実です。私が勤務している琉球大学附属図書館に「久米島出張復命書」という資料があります。この中に、「県令(中央政府から派遣された知事)は本土に逃げ帰っている」「もうすぐ清の戦艦がやってくる」といった噂が沖縄社会で広まっていたことが記述されています。日本の支配に抵抗する旧士族層が流していたのですが、この噂を信じ、那覇から本島北部のやんばるに避難した人もいました。こうした当時のリアリティも念頭に置くと、交渉の背景が浮かびやすいと思います。結論から言えば、交渉は日清間で棚上げになり、最終的には日清戦争で日本が勝ち、台湾が日本の植民地になることで宮古・八重山を含む日本領土が画定しました。
沖縄で戦争というと、沖縄戦に話題が集中しますが、琉球処分の段階から有事になる可能性があったということです。日清戦争では志願した職業軍人だけでしたが、日露戦争からは徴兵された沖縄の男性が戦地に送られ、国民として日本の戦争に参加していく時代に移行したことは沖縄の近現代史を振り返る上で重要です。
―沖縄の人が「日本人」になったことで、日本の戦争に参加することも余儀なくされたということですね。
前田 日露戦争では徴兵された多くの県民が亡くなりました。しかし、沖縄世論は厭戦感情に包まれるわけではなく、戦死者を顕彰する「招魂祭」が各地で盛大に催されました。これは現代の慰霊祭とは異なり、亡くなった兵士を地元のヒーローとして称えるイベントです。日清・日露戦争の勝利を経て日本のナショナリズムが盛り上がる過程で、沖縄もこれに同期し、その延長線上に「県民総動員」といわれる沖縄戦に突入していきます。